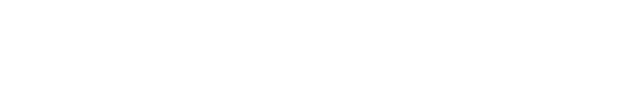医療機関が支える、安心のストレスチェック-中小企業のための、わかりやすい一律料金プラン-
中小企業向けストレスチェック|医療機関が支える安心の全国対応サービス
ストレスチェック義務化に対応|中小企業・50人未満でも安心
なぜストレスチェックが義務化されたのか
ストレスチェック制度は、職場におけるメンタルヘルス不調を早期に発見し、従業員の健康を守るために義務化されました。
特に現代の職場では、長時間労働や人間関係の悩みなど、心の不調につながる要因が増えています。
50人未満の事業所でも早めの導入が安心な理由
現在は従業員50人以上の事業所に義務付けられていますが、今後はすべての企業に拡大される見込みです。
従業員数が少ない中小企業こそ、早めにストレスチェックを導入することで職場環境の改善や離職防止につながります。
当院のストレスチェックサービスの特徴
医療機関による実施とフォロー体制
当院は精神科クリニックが直接運営するサービスです。
単なる検査にとどまらず、必要に応じて医師による面談やアドバイスを行い、従業員の心のケアを手厚くサポートします。
担当者の負担を最小限にする仕組み
中小企業では人事担当者が他業務を兼務していることも多く、制度対応が大きな負担になりがちです。
当院では案内文作成、集計、結果返却、集団分析まで一括対応。担当者様は最小限の手間で導入できます。
法令要件を満たす正しい運用
厚生労働省が推奨する調査票を使用し、法令に準拠した方法で確実に実施。
検査結果等報告書の作成・提出まで責任をもって対応します。
日本全国どこからでも対応可能
全国どこからでもストレスチェックの実施が可能。
必要な書類などはすべて郵送で対応できます。
医師面談まで可能
メンタルクリニックが実施するストレスチェックサービスのため、面談の際に新たに医師を手配する必要がありません。
ストレスチェック実施の流れ
フォームからお申し込み
申込みフォームから、対象従業員の人数などを入力して下さい。
3営業日以内に見積書をメールにてお送りします。
ストレスチェックの実施
人数分のチェックシートと返送用封筒を郵送します。
従業員の方は短時間の質問に回答するだけ。
誰でも取り組みやすい仕組みです。
記入済みのチェックシートをまとめて当院まで返送して下さい。
結果返却と集団分析レポート
分析後、個人ごとの結果をそれぞれ封緘し、まとめて送付します。
担当者様は、開封せずに従業員の方にお返し下さい。
また、全体の傾向をまとめたレポートも作成し一緒に送付します。
職場改善の材料として活用できます。
高ストレス者への医師面談
必要に応じて精神科専門医が30分の面談を実施。
早期発見と適切な対応で、従業員のメンタルヘルスをしっかり支えます。
検査結果等報告書の作成・提出
法令に基づいた報告書を作成し、企業様に代わって提出。
安心して任せていただけます。
わかりやすい一律料金プラン
基本プラン|ストレスチェック一律10万円
従業員数にかかわらず、一律料金でストレスチェックを実施。明瞭な費用体系で導入しやすいのが特徴です。
追加料金の仕組み(30名以上)
31人目以降は1名あたり1,000円の追加料金。従業員が増えてもシンプルで分かりやすい料金設定です。
医師面談オプション(1人30分 20,000円)
高ストレス者への面談は、1人あたり30分20,000円で対応。
必要な場合のみ追加で実施できるので無駄がありません。
※上記価格は税抜きになります。
よくある質問(FAQ)
個人情報の取り扱いについて
個人結果は本人のみに返却され、企業に個別の内容が伝わることはありません。
法令に準拠し、プライバシーを厳守します。
実施にかかる期間の目安
人数や方法により異なりますが、最短で数週間程度で実施可能。
スケジュールに合わせて柔軟に調整します。
報告書提出は任せられる?
はい。検査結果等報告書の作成から提出まで当院が代行いたします。
支払のタイミングは?
人数分のチェックシートを送付する際に、請求書を同封いたします。
お支払いは銀行振込のみとなります。
ストレスチェック結果は振込確認後に返送いたします。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
「制度のことを一から教えてほしい」「導入にあたり不安がある」など、どのようなご相談も大歓迎です。
まずはお気軽にお問い合わせください。日本全国対応いたします。
巻末コラム:ストレスチェックとは??
制度の成り立ちと背景
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的に、2015年12月に労働安全衛生法の改正によって導入されました。
背景には、うつ病や適応障害といった精神疾患による休職や離職が増加し、労働損失が社会全体の大きな課題となっていたことがあります。
厚生労働省の調査によれば、「強い不安やストレスを感じている」と答える労働者は半数を超えており、職場におけるメンタルヘルス対策の必要性が高まっていました。
これまで制度は「労働者数50人以上の事業場」に限って義務化されてきましたが、2025年の法改正により、規模を問わずすべての事業場で実施が求められる見込みです。
つまり、従業員数が数名の小規模な事業場でも例外ではなくなるという点で、大きな転換点を迎えています。
ストレスチェックの仕組み
ストレスチェックは、簡単に言えば「従業員がどれだけ心理的な負担を抱えているか」を定期的に把握するための仕組みです。主な流れは以下のようになります。
-
質問票による調査
厚生労働省が推奨する57項目の質問票を用いるのが標準です。質問は大きく分けて-
仕事のストレス要因(業務量、裁量の有無、人間関係など)
-
心身のストレス反応(疲労感、不安感、意欲の低下など)
-
周囲からのサポート(上司や同僚からの支援の有無)
の3つの側面を調べるもので、短時間で回答できる形式になっています。
-
-
個人への結果通知
調査結果は本人に直接通知されます。従業員は自分のストレス状態を客観的に把握し、必要に応じてセルフケアにつなげることができます。 -
高ストレス者への医師面接
判定の結果、高ストレスとされた人には医師による面接指導の機会が用意されます。本人の希望に基づいて行われ、勤務状況の調整や治療への橋渡しが検討されます。 -
集団分析による職場環境改善
個人を特定できない形でデータを集計すると、職場単位の傾向が見えてきます。「残業が多い部署はストレス反応も強い」「上司からのサポートが不足している」といった課題が浮き彫りになり、職場環境改善の具体的な材料になります。
ストレスチェックの目的と意義
ストレスチェックは「病気を診断するための検査」ではありません。
最大の目的は 不調を未然に防ぎ、早期に気づくこと にあります。
従業員一人ひとりが自分の状態に気づき、必要なら相談や受診につなげられる点が大きな特徴です。
また、組織としても「個人に責任を押し付ける」のではなく、「職場全体の改善に活かす」ことが求められています。
例えば、データから「人手不足による業務量の過多」が明らかになれば、単なる個人指導ではなく、業務配分や人員体制そのものの見直しが必要になるでしょう。
中小企業にとっての意味
中小企業では、従業員一人が担う役割が大きく、誰かが不調に陥ると職場全体の機能が低下するリスクがあります。
また、規模が小さいほど「相談先がない」「不調を抱えていても周囲に気づかれやすい」といった問題も生じがちです。
ストレスチェックはこうしたリスクを可視化し、早期に対応するための有効なツールとなります。
さらに、制度を上手に活用することで、以下のような副次的な効果も期待できます。
-
従業員が「自分の健康に配慮してもらえている」と感じることで組織への信頼感が高まる
-
健康経営の一環として社外にアピールでき、採用や取引にプラスに働く
-
客観的なデータに基づいて改善を進められるため、経営判断の材料になる
まとめ
ストレスチェックは、単なる「法律で決められた義務」ではなく、従業員の健康を守り、企業の生産性と信頼性を高める仕組みです。
中小企業にとっては導入のハードルもありますが、外部サービスや簡易ツールを活用すれば、負担を最小限に抑えながら実施することが可能です。
制度の本来の目的を理解し、「義務対応」にとどめず「組織を良くするための投資」として取り組むことが、これからの時代を乗り越えるための大きな力になるでしょう。