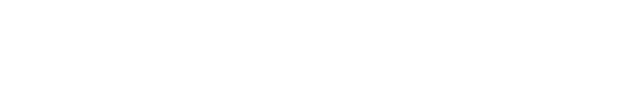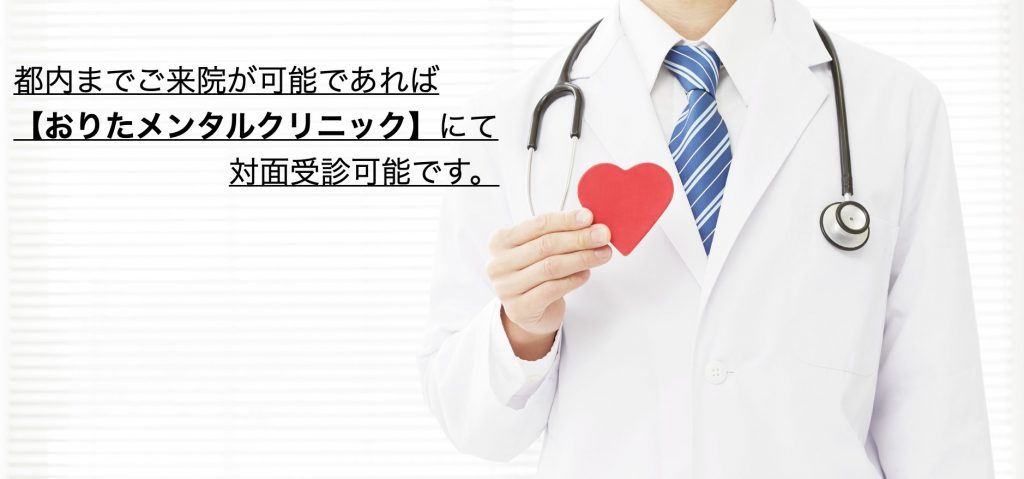強迫性障害とは?
「電気を消したかな?」「玄関の鍵をかけたかな?」と不安になってしまい、何度も確認してしまう・・・このような経験はありませんか?
たまに確認するというのなら問題はありませんが、どうしても何度確認しても安心できないという症状があれば、強迫性障害の可能性があります。
「手が汚い」「手に雑菌がついて落とすことができない」などと思ってしまい、何度も何度も手が荒れるほど繰り返し手を洗ってしまう行為も強迫性障害の1つ。
他にはどんな症状が強迫性障害なのでしょうか?今回は強迫性障害の症状から原因・治療にいたるまで幅広く解説していきます。
強迫性障害とは
強迫性障害とは、“強迫観念”と、その強迫観念に対処しようとする“強迫行為”が生じる病気のことです。
自分の意思に反してある考えが頭に浮かんで、追い払うことができず(=これを、強迫観念といいます) 、
その強迫観念で生まれた不安を振り払おうと、何度も何度も同じ行為を繰り返してしまいます (=これを、強迫行為といいます) 。
またその不安は「不条理でつまらない」「不安でやりすぎだ」と自分でもわかっていても、止められないのが強迫性障害の特徴です。
不条理だと理解しながらも同じ行為を繰り返さずにはいられないため、強迫性障害は日常生活に大きな支障をきたします。
強迫性障害になる人は100人に2-3人程度と言われており、男女比は半々です。
また、平均年齢は20歳程度と比較的若年で、35歳以降で発症するのは比較的まれです。
ただし発症してから受診に至るまでは比較的長く、中年以降で初めて受診するケースも多いです。
他にはうつ病や他の不安障害(パニック障害・社会不安障害など)の併発も多く見られるのも特徴の1つです。
強迫性障害の症状
代表的な強迫観念・強迫行為に以下のようなものがあります。
【不潔恐怖・洗手強迫】
ドアノブや手すり、つり革など、不潔に感じてに触れない。
汚れや汚染の恐怖から過剰に手洗いを行う。
(行動例)手洗いを繰り返しすぎて、手荒れ・肌荒れを起こすことが多い。
【確認行為】
戸締まり、鍵の確認を繰り返す。
ガスの元栓の締め忘れ、電気の消し忘れなどの確認を繰り返す。
(行動例)繰り返し確認しても不安になる。そのため出かけるまでに時間がかかり、遅刻を繰り返す。
また、外出しても不安になって帰宅してしまう。毎回スマホでスイッチ類の写真を撮って安心を得ようとする人もいる。
【加害恐怖】
「歩行中、人にぶつかってしまったのではないか」
「運転中、何かにぶつけてしまったのではないか」
など、気づかずに他人に危害を加えてしまったのではないかという不安が、頭から離れない。
(行動例)他人に何度も確認したり、被害届が出ていないか警察に確認したりする。
【強迫儀式】
自分なりの順序・方法で物事を進めなければならないというこだわり。
(行動例)入浴や着替えなど、順序を間違えると最初からやり直さなければならず、時間がかかる。
【物事へのこだわり】
家具や小物(リモコンなど)の配置に過剰にこだわる。
(行動例)曲がっていたり、場所が変わっていたりすると、必ず戻す
重症化すると自分だけでなく、周りに一種の「こだわり」を押し付けるようになり、社会性が失われてしまいます。
強迫性障害の症状は、誰もが生活の中で気になること(玄関の鍵の確認や手洗いなど)のほんの延長線上にあるのが一般的です。
そのため 「少し神経質なだけ」なのか「行き過ぎか」という判断は非常に難しいところです。
強迫性障害は、重症化してしまうと治療による改善が難しくなり、自殺の可能性も高まってしまうと報告されています。
強迫観念や強迫行為で ’日常生活・社会生活に影響が出ている’ ‘家族や周囲の人が困っている’ といったサインがある場合には、早期に治療を開始することが推奨されます。
強迫性障害はどのような人がなりやすい?
強迫性障害は、真面目で几帳面な人がなりやすいと言われています。
完璧主義で曖昧さが許容できない人などは注意が必要です。
国内では100万人以上の患者がいると言われており、決して稀な病気ではありません。
強迫性障害の原因
強迫性障害の原因や発症に関してはっきりとした原因は特定されていません。
しかし、神経学的な要因や環境にも原因があるのではないかと研究が進められています。
神経要因
脳内伝達物質であるセロトニンの不足が関わっている可能性が指摘されていますが、明確には解明されていません。
環境要因
ストレスや環境の変化などが関わっていることが多いと言われています。
女性の場合は、月経前や出産後に生じやすいと言われています。さらに、強烈なトラウマになるような出来事を経験したあとも発症しやすいことが報告されています。
強迫性障害は心配性や潔癖症と違う?
日常生活に支障をきたしているかどうか、が診断のポイントになります。
心配しがちな性格や、潔癖な人だとしても、家庭生活や仕事で問題がなければ(自分なりに不安に対処できているのであれば)、病気=強迫性障害ではないと考えられます。
ただし日常生活を送る上で、あるいは社会的に問題が起こるのであれば、それは治療が必要な病気=強迫性障害の可能性があると言えるでしょう。
(例)遅刻を繰り返す。常に手荒れ・あかぎれ。外出が不安で引きこもる。
どのタイミングで受診すべき?
どのタイミングで受診すべきか、自分自身では判断しにくいことも多いのがこの強迫性障害です。
家族や友人から指摘されて受診に至るケースも多くあります。
「バカバカしいと思っていても、繰り返してしまう」
「(強迫行為を)やめたいのに、やめられない」など、
矛盾を感じて苦しんでいるのであれば、一度受診するべきでしょう。
強迫性障害の診断・重症度評価
強迫性障害は、一般的な病気のように血液検査や画像検査で異常が見られません。
そのため、症状の程度、日常生活の困難さなど、さまざまな状況を総合的に判断して診断が下されます。
なお、アメリカ精神医学会の最新の診断基準では、主に以下の4つの項目で強迫性障害と診断するとしています。
・強迫観念または強迫行為もしくはその両方が存在する
・強迫観念や強迫行為のために時間を浪費し、社会生活や日常生活に支障をきたしている
・強迫観念や強迫行為は、薬物やアルコールなどの乱用・その他の病気が原因ではない
・他の精神障害(全般性不安障害・統合失調症など)の診断に適さず、強迫性障害の症状に最もよくあてはまる
上記のものは、実際の診断基準を簡略化し記載したものです。
また、重症度評価については’’エールブラウン評価スケール’’というものを用い、強迫観念・強迫行為の程度を評価します。
具体的には、それぞれ強迫観念・強迫行為について
・どれだけ時間を費やしてしまうか
・社会活動・仕事(学業・家事)への支障の程度
・苦痛の度合い
・症状にどのぐらい抵抗しようとしているか
・症状をどのぐらいコントロールできるか
についてそれぞれ0-4点の5段階で評価します。
そして、強迫観念5項目、強迫行為の5項目の得点を合計した40点満点の点数で重症度を判断します。
点数に対応した重症度は以下のようになります。
| 0-7点 |
【病気ではない】 |
| 8-15点 |
【軽度】 必ずしも日常生活や社会参加に支障をきたすほどではない 他人より作業にいくらか時間がかかってしまうことがある |
| 16-23点 |
【中等度】 社会生活に支障をきたし、苦痛がある 独力では、症状のコントロールが難しい |
| 24-31点 |
【重症】 重大な生活機能の障害を引き起こし、他者からの援助が必要である 通勤、通学、日常生活が非常につらい |
| 32-40点 |
【極症】 生活の大半が症状に費やされ、周囲の人の多大な援助が必要となる 引きこもり状態の人が多い |
重症度評価は初診時の評価に重要なだけでなく治療の効果判定にも使うことができます。
強迫性障害の治療
強迫性障害の治療は、精神療法と薬物療法を組み合わせて行います。
強迫性障害の方は、不合理な不安や考えであるとご自身も自覚されている方が多く、そのため周囲の誰にも症状の相談をできずに、抱え込んで落ち込んでしまう傾向にあります。
そのために、強い不安や・抑うつ症状から、うつ病や不眠などを併発していることも少なくありません。
まずは薬物療法を用い抑うつ・不安症状の改善に努めます。
そして、強迫性障害の中心的な「強迫観念」と「強迫行為」の強固なサイクルの見直しと改善のために精神療法を行うことが望ましいとされています。
精神療法と薬物療法について具体的に確認していきます。
精神療法
精神療法では、曝露反応妨害法が代表的です。
曝露反応妨害法とは、強迫観念による不安に立ち向かい、強迫行為をしないで我慢するという課題を繰り返すことで、強迫行為をしなくてもよくなっていくことを目標とする行動療法です。
例えば、汚いと思うものを触って手を洗わないで我慢する、留守宅が心配でも鍵をかけて外出し施錠を確認するために戻らないで我慢するといった課題を繰り返します。
こうした課題を不安度の低い強迫行為から続けていくことにより、ご自身の不安感情が制御可能な範囲になることを自覚してもらい、強い不安も徐々に弱まってゆき、やがて強迫行為をしなくてもよくなっていくという流れです。
強迫性障害の人は、恐怖の対象となる刺激に遭遇することで強迫観念が呼び起こされ、それを打ち消そうと強迫行為を繰り返すようになりますが、強迫行為をしても強迫観念が消えるほどの効果は持ちません。
一時的に安心感を味わうために、強迫行為を行ってしまうものの、安心感はすぐ薄れていくので強迫行為を延々と何度も行ってしまいます。
曝露反応妨害法は、この負の連鎖を断ち切るための治療法であり、大きな効果を持つことが実証されています。
もちろん、不安度の高い強迫行為に対して突然このような療法を急に行うと、反対にパニック発作などを誘発する恐れがあるため、無理に療法を行うのではなく、あくまでも「一つ一つの成功を着実に重ねていく」という点が重要です。
薬物療法
強迫性障害に対する薬物療法は、「精神療法を進めるためにまず気持ちを落ち着けること」「強迫観念による不安を少しでも薄れさせること」を目的とします。
そのため使用するお薬はセロトニンの働きを強める抗うつ剤、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)が基本となります。
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、強迫性障害の原因の1つと考えられている脳内のセロトニン系の異常を調整する働きを持ちます。
うつ病にも効果を発揮しますが、脳内セロトニンの濃度を減らさないように作用することで強迫行為への衝動を和らげる効果もあります。
強迫性障害は、うつ病の場合よりも高用量で長期間の服薬が必要となることが多いですが、不安にならず決まった用量を定期的に内服することが重要です。
その他に、SNRI(セロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害薬)・クロミプラミン(三環系抗うつ薬)が治療薬として使用されます。
SNRI(セロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害薬)は、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)と似た薬であり、強迫性障害に対する治療効果が期待されていますが、まだ十分に有効性があるかは判明していません。
クロミプラミン(三環系抗うつ薬)は、強迫性障害の症状を和らげる効果が立証されていますが、口渇・便秘・眠気・ふらつきなどの副作用が強いため、非常に注意が必要な薬です。SSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)で効果がなかなか得られない場合に使用することがあります。
これらのお薬で強迫性障害の状態を安定させた上で、認知行動療法を行なうのが一般的です。
ただし強迫性障害の治療の前提として、患者自身が治そうという意思を持っていることが大切です。
強迫性障害を治そうという意思を維持するための心理的介入も必要となることもありますが、
治療する意志を維持することで積極的に治療を行うと、良好な治療結果が得られやすくなります。
家族への弊害
強迫性障害はその疾患特性上、家族を巻き込んでしまうケースもあります。
患者は自身の強迫行為を家族にも強制することもあるため、それに付き合いきれない家族が疲弊することもしばしばあります。
具体的には、家族にも過剰に手洗いや除菌を要求したり、特定の場所にさわることを禁じたりするなどです。
患者自身は家族に自分の強迫観念を理解されないことから、不安や怒りを感じ、家族関係が悪化することもあります。
また、対応に苦慮した家族がうつ病になることもあり、注意が必要です。
強迫性障害の治療開始後・再発予防に向けて
治療を始めた後も、自分のために自分で治そうと継続して思うことが大切です。
薬物も自己中断せず、決められた用量を決められた通りに服薬するよう心がけて下さい。
また強迫性障害には、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら改善していくという特性があるため、一喜一憂せず、受診・治療を地道に継続することが必要です。
また、この病気は引きこもりや生活リズムが乱れると悪化するため、規則正しい生活や睡眠、外出を心がけ、学校や仕事などの社会的関わりは、可能な限り継続することをお勧めします。
病気から「逃げない、繰り返さない」という行動・正しい生活習慣がしっかりと身につけば、病気は良くなっていきますし、再発率も非常に低くなります。
記載:おりたメンタルクリニック医師
■オンライン診療メンタルヘルス院について■
休職相談を扱う"オンライン診療専門"の
「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。
休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。