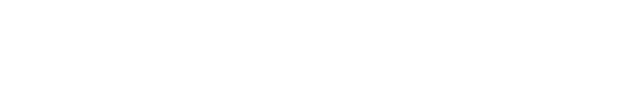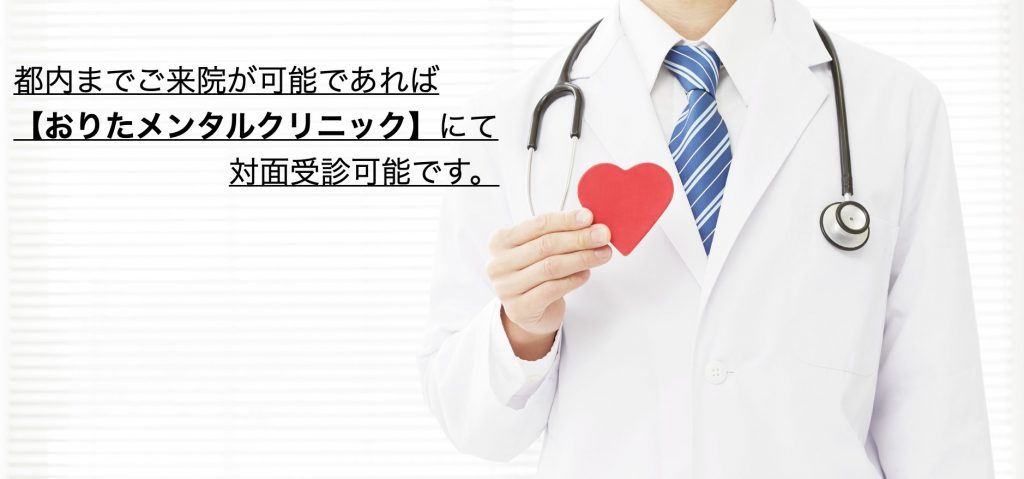うつ病の相談・治療
心が晴れない方へ。「うつ病」の症状や治療方法について解説
「何をしても楽しめない・・・」
「一日中気分が落ち込んでいる・・・」
日常生活の日々に疲れてしまって、心が晴れない方。
もしかすると、それは「うつ病」なのかもしれません。
うつ病はどんな病気なのか良く知って正しく対処することで、徐々に改善していく病気です。
逆に「うつ病」だと自己判断し、間違った対処をしていると治らないばかりか、徐々に悪化してしまうことも。
この記事では「うつ病」について診断基準から治療方法に至るまでわかりやすく解説します。
目次
・まとめ
・コラム
うつ病とは?
うつ病とは「精神的ストレスや身体的ストレスをきっかけに、脳がうまく働かなくなっている状態」です。
脳のエネルギーがなくなっている状態とも言えます。
日本では100人に約6人が生涯のうちにうつ病を経験しているといわれており、決して珍しい病気ではありません。
また、女性のほうが男性よりも1.6倍多いことがいわれています。
うつ病の症状は?
うつ病といっても、その症状の現れ方はとても様々。
また、そう状態とうつ状態を繰り返す双極性障害という病気もあります。
それぞれに合わせて治療法が大きく異なるので、専門家による診断が必要な疾患です。
また、うつ病の重症度によっても異なります。重症度に分けた症状の現れ方は以下の通りです。
① 軽症の場合
軽症の場合は、「なんとなく疲れている」「なんとなく何事に対してもやる気がでない」感じがあるものの、本人も「単なる疲れ」と感じてしまい放置しがち。
そのため仕事や日常生活で多少他人とのコミュニケーションなどに違和感を覚えることがあるものの、自覚していないこともあります。
周囲の方も本人の変化にあまり気が付かないこともしばしばです。
他には、たとえば次のような精神症状がでてきます。
【精神症状の例】
- 気分が落ち込む
- 無関心になる
- 不安やあせり・イライラ感がでてくる
- 仕事に集中できず、ミスが増えてしまう
- 悲観的に物事を考えがちになってしまう
- 飲酒量が増える
- 外見や服装を気にしなくなる
- 口数が少なくなる
② 中等度の場合
「やる気が出ない感じが」が徐々に出てきて、睡眠不足も見られることもあります。
そのため、仕事のパフォーマンスも低下してきて、他の人も違和感を覚えることも多いでしょう。
本人も自力で頑張ってしまうこともあり、仕事ができない自分を責めてしまう場面も出てきます。
また中等度になると、次のような身体症状も出ることもしばしばです。
【身体症状の例】
- 頭痛
- 耳鳴り
- 睡眠障害(不眠・過眠)
- 動悸
- めまい
- 肩こり
- 性欲減退
- 下痢や便秘
- 生理不順
- 食欲低下
- 息切れ
③ 重度の場合
仕事や日常生活や他人のコミュニケーション自体が、明らかに困難なレベルになります。
特に「自分がいなくなった方がよいのではないか」など希死念慮が出てくるケースもあります。
しばしば現実に行為に至ってしまったり、入院が必要なケースも出てきます。
このように、重度になった場合「死ぬリスク」もあるのがうつ病の特徴です。軽症の段階でいかに早く見分けるかが重要な疾患といえるでしょう。
うつ病になりやすい人とは
従来、うつ病になりやすい人の気質を、メランコリー親和型気質と言います。
こういう気質を持つ方には以下のような特徴があります。
メランコリー親和型性格の特徴
うつになりやすい性格
律義さ、秩序愛
真面目な性格
仕事に対して緻密、入念、几帳面で自己要求が高い
周囲への配慮がある
他人のために尽くすことで秩序を守ろうとする
仕事に熱心に取り組む
責任感がある
問題に対して自分一人で解決しようとする
食欲不振、不眠がある
心身の疲労がある
うつであることを隠そうとする
真面目すぎて融通が利かない人が多い
病気やけがなどの不時の出来事で秩序が乱されることが危機的状況へとつながる
うつ病の原因は?
うつ病の発症の原因は正確にはよくわかっていません。
感情や意欲を司る脳の働きに何らかの不調が外部からのきっかけで一時的に生じているものと考えられています。
うつ病の背景には、よく精神的ストレスや身体的ストレスが指摘されますが、一概にはそうとも言えないことも。
辛い体験だけでなく、結婚や就職など一見「喜ばしい出来事」もうつ病の発症のきっかけになることもあります。
前述の通り、妊娠や更年期などをきっかけにすることもあります。
いずれにせよ、一時的な心の不調であることが多く、放置せず正しく対処すれば重症には至りません。
ただし、放置すると時間と共に悪化するようになると、仕事や家事・勉強など本来の社会的機能がうまく働かなくなり、人との交際や趣味など日常生活全般にも支障をきたすようになります。
うつ病の原因や治療に関わる神経伝達物質「セロトニン」
うつ病の発症の原因はわかっていないことも多いものの、さまざまな研究でうつ病の発症原因に欠かせない神経伝達物質として「セロトニン」の関与がわかっています。
セロトニンとは脳内の神経伝達物質の1つで、ドパミン・ノルアドレナリンをコントロールし、精神を安定させる働きがあります。
必須アミノ酸であるトリプトファンから体内で合成され、脳内の中枢である「視床下部」「大脳基底核」などに高濃度に分布しています。
セロトニンが低下すると、ドパミンやノルアドレナリンのコントロールが不安定になり、攻撃性が強くなったり、不安やうつ症状などの精神症状を引き起こすことがわかっています。
うつ病の改善にはセロトニンの分泌を増やすことは欠かせない要素なのです。
<参考までに>
悲しみや幸せなど感情的な症状は「腹内側前頭前皮質」と「扁桃体」で調節されているとされています。
・扁桃体、前頭前皮質→罪責感、自殺傾向、無価値観などに関与すると考えられている
・側坐核→楽しみ、興味、活動性の低下に関与すると考えられている
・視床下部はうつ病に関する睡眠と食欲に関連すると考えられている
症状から責任部位を推測すると
・抑うつ気分→扁桃体、腹内側前頭前皮質(前頭前皮質の感情の領域)
・無気力、興味の喪失→前頭前皮質(腹内側・背外側)、視床下部(情動の中枢)、側坐核(喜び・興味の中枢)
・遂行機能不全→背外側前頭前皮質
と考えられています。
うつ病の治療は?
このように近年の研究で、うつ病ではセロトニンをはじめとした多くの神経伝達物質のバランスの乱れにより引き起こされることがわかってきました。
このことから、うつ病の治療は、「神経伝達物質を整える薬物治療」「休養や環境の調節」「精神療法」「そのほかの治療法」に分けられます。
① 神経伝達物質を整える薬物治療
うつ病の治療にはセロトニンやノルアドレナリン・ドパミンのバランスの乱れによって引き起こされることがわかっています。
そのため、うつ病の薬物治療の中心はSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)と呼ばれる「抗うつ薬」です。
これらの薬物は、放出されたセロトニンを体内に再度取り込みさせないようにすることで、体内のセロトニンの血中レベルを上げ、神経伝達物質の調整に関わります。
他にも精神安定に関わる神経伝達物質「GABA」のレベルを上げる「抗不安薬」「睡眠導入薬」、他の神経伝達物質のレベルを調節する「非定型抗精神病薬」などがあげられます。
人によって薬物による効果に違いがありますが、うつ病の主な薬は飲んですぐに効くものではありません。徐々に体内に「蓄積される」治療といっても過言ではありません。そのため、焦らずに薬の服用をつづける必要があります。
薬を勝手に中断したり量を増やしたりせずに、必ずかかりつけの先生の指示に従って服薬するようにしましょう。
② 休養や環境の調節
継続した薬の治療と共に大切なのは、環境の調節や休養です。
うつ病は脳のエネルギーが枯渇した状態といえるので、十分な休養をとって心と体を休ませることはうつ病治療の第一歩です。
睡眠を十分とるのはもちろんのこと、職場や学校、家庭などでうけるストレスを軽減できるように環境調節することはとても大切になります。
もともとうつ病になる方は、「真面目」で「責任感が強い」方が多いので、休養をとったり環境をがらっと変えてしまうことに抵抗を覚えてしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、ご自身の健康あっての仕事であり人生であり、家族です。
ご自身のためだけでなく、周りの家族のためにも、あせらずに休養を取って自分の出来ることを無理なく出来る環境を作ることは何の恥でもありません。
かかりつけの先生と相談し、周りの環境を整えるようにしましょう。
睡眠や環境の他にも、規則正しい生活やバランスの取れた食事は、セロトニン合成のためにもとても重要です。
自分で出来ることから始めてみましょう。
③ 精神療法
十分な休養や環境の調節・神経伝達物質の調節を行うことで、多くの方のうつ病は自然と改善していきます。
しかし、中には「なぜうつ病になったかわからない」「ストレスの解決策が見つからない」という方もいらっしゃり、そのような方はしばしば上記の治療法を組み合わせても、治療が難渋することがあります。
そうした方も有効なのが「精神療法」です。
ストレスの原因を振り返って自分で対処法を学び、調子のよう状態を維持する。
これが精神療法の目的です。
最も一般的なものに「認知行動療法」があります。
【認知行動療法とは】
認知行動療法とは、「自分がどのように現実を受け取っているか」を客観的に知ることで、正しい認知に置き換え、行動を変えていく治療法です。
人間は何か出来事が起こった時に、ぱっと思い浮かぶ「自動思考」というのが備わっています。
例えば、道に迷った時に「人に聞けばいいや」と楽観的になる人もいますし「もっと準備しとけばよかった」「自分ばかり悪いことが起こる」と悲観的になってしまう方もいます。
それは誰から教えられたわけでなく「勝手に」湧き上がってくる思考回路です。
これを「自動思考」といいます。
実際には、道にまよったとしても人に聞くなり、地図をみるなり、様々な対策手段があるはずです。
これを実際に行動し、「こういった方法もあるんだ」と学ぶことで次に同じようなストレスが起こっても適切に対処できるようにする。
これが「認知行動療法」の1つです。
④ そのほかの治療法
その他にも「運動療法」「修正型電気けいれん療法」「高照度光療法」「経頭蓋磁気刺激療法」など様々な治療法があります。
まとめ:心が晴れず「うつ病」になっている方へ
うつ病でお悩みのあなた。
決して一人で悩まないでください。
うつ病は治らない疾患ではありません。
ただ、適切に対処せず自分の心を放置すると悪化して、最悪「死ぬリスク」も背負ってしまうことになります。
逆に言えば適切に対処すれば治る疾患です。
ぜひあきらめないで、精神科・心療内科などでカウンセリングを受けてみてはいかがでしょう。どうか一人で抱え込まないでください。
うつ病にまつわるコラム
コラム1: うつ病の診断基準について
下のDSM-5はうつ病の診断基準の一つになります。他にも複数の基準がありますし、経過、症状、診察での様子など、様々な要因から診断に至ります。
診断基準はあくまで参考とし、医師の診察、指示に従うようにお願いします。
【うつ病(大うつ病性障害)の診断基準(DSM-5)】
A: 以下の症状のうち5つ (またはそれ以上) が同一の2週間に存在し、病前の機能からの変化を起している; これらの症状のうち少なくとも1つは、1 抑うつ気分または 2 興味または喜びの喪失である。 注: 明らかに身体疾患による症状は含まない。
1. その人自身の明言 (例えば、悲しみまたは、空虚感を感じる) か、他者の観察 (例えば、涙を流しているように見える) によって示される、ほとんど1日中、ほとんど毎日の抑うつ気分。注: 小児や青年ではいらいらした気分もありうる。
2. ほとんど1日中、ほとんど毎日の、すべて、またはほとんどすべての活動における興味、喜びの著しい減退 (その人の言明、または観察によって示される)。
3. 食事療法中ではない著しい体重減少、あるいは体重増加 (例えば、1ヶ月に5%以上の体重変化)、またはほとんど毎日の、食欲の減退または増加。 (注: 小児の場合、期待される体重増加が見られないことも考慮せよ)
4. ほとんど毎日の不眠または睡眠過多。
5. ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止 (ただ単に落ち着きがないとか、のろくなったという主観的感覚ではなく、他者によって観察可能なもの)。
6. ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退。
7. 無価値観、または過剰あるいは不適切な罪責感 (妄想的であることもある) がほとんど毎日存在(単に自分をとがめる気持ちや、病気になったことに対する罪の意識ではない)。
8. 思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日存在 (その人自身の言明、あるいは他者による観察による)。
9. 死についての反復思考 (死の恐怖だけではない)、特別な計画はない反復的な自殺念慮、自殺企図、または自殺するためのはっきりとした計画。
B: 症状は臨床的に著しい苦痛または社会的・職業的・他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
C: エピソードが物質や他の医学的状態による精神的な影響が原因とされない。
※出典元:精神疾患の診断・統計のマニュアル アメリカ精神医学会 Washington,D. C.,2013(訳:日本精神神経学会)
コラム2: 身体疾患により引き起こされるうつ病
うつ病でなくとも、以下のような身体疾患からうつ状態が引き起こされることがあります。
そのため身体疾患が隠れていないかどうかも、診断の大切なポイントになります。
脳器質疾患
脳血管障害、脳炎、頭部外傷、脳腫瘍、アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病、正常圧水頭症、側頭葉てんかんなど
代謝疾患
ペラグラ、ビタミンB12欠乏症など
内分泌疾患
甲状腺機能亢進または低下、副腎皮質機能亢進または低下
自己免疫性疾患
SLE,RAなど
ウイルス性または他の感染症
インフルエンザ感染、肝炎、単球増加症、HIVなど
癌
膵癌など
脳血管障害によるうつ
脳梗塞により情動を司る神経ネットワークの一部が障害され発症する
薬物誘発性うつ病
注意すべき薬剤は以下のようなものが挙げられます。
ステロイド、インターフェロン、甲状腺ホルモン、β遮断薬など
コラム3: うつ病で見落とされがちな「躁うつ病」について
躁うつ病(双極性感情障害)≠うつ病
躁うつ病とうつ病は全く異なる病気です。
・うつ病の男女比は男:女=1:2ですが、躁うつ病は1:1と大きく異なります。
・治療についても異なり、躁うつ病については躁状態を安定させるために非定型抗精神病薬など、抗うつ薬以外を使うこともあります。
躁うつ病(双極性感情障害)の種類
双極Ⅰ型: 少なくとも1つの躁病、あるいは混合性(同時に完全な躁病と完全なうつ病であること)エピソードの発生、大うつ+、躁+、(混合性障害+)
双極Ⅱ型: 1つあるいはそれ以上の大うつ病エピソードと少なくとも1つの軽躁病エピソード、大うつ+、軽躁+
※躁と軽躁の違いは、社会活動や人間関係に大きな問題を生じるかどうか
躁うつ病になりやすい性格
循環気質
躁うつ気質。クレッチマーの分類の一つ。
・社交的、善良、親切、温厚
・明朗でユーモアがあり活発(軽揚型)
・静か、平静、気重、感じやすい(抑うつ型)
執着気質
躁うつ病の病前性格として下田光造氏が提唱した。
感情の経過の異常(一度起こった感情が、持続的に緊張・持続あるいは増強し減退しない。一度着手したことは徹底的にやらねば気が済まない)
・仕事熱心
・凝り性
・徹底的
・正直
・几帳面
・強い正義感や義務責任感
・ごまかしやずぼらができない
・他人からは模範的な人物、信頼すべき人物、真面目な人と見られている。
※執着気質: 強力的であり周囲を巻き込む
⇔メランコリー親和型: 弱力的であり、周囲を巻き込まない。周囲に気を遣う。
双極性うつの特徴
・双極性障害の家族歴、若年発症、過眠、食欲亢進、気分症状の不安定さ、うつ病相の再発を繰り返す
コラム4: うつ病以外にも使われる抗うつ薬-疼痛の場合-
痛みを伴う精神疾患にも、抗うつ薬を使用することはよくあります。
抗うつ薬の適応は
・心因性疼痛
・神経因性疼痛
つまり・・・
・身体表現性障害(身体表現性疼痛障害、転換性障害、身体化障害、心気症)
・うつ病、双極性障害その他の気分障害
・不安障害(全般性不安障害、パニック障害など)
などになります。
<慢性疼痛治療における抗うつ薬選択の目安>
SSRI: うつ病、身体表現性障害に伴う心因性疼痛に効果が期待できると言われている。
SNRI: SSRI対象疾患に加え、神経因性疼痛、とりわけ整形外科領域で扱う痛みなど。顎関節症、舌痛症など口周囲の痛みにも使用することはある。
三環系抗うつ薬: 以前からある抗うつ薬だが、未だに痛みに対してもよく使われる。副作用に注意する必要がある。
<抗うつ薬以外の処方の一例>
抗けいれん薬: 「電気が走る」「鋭い」「刺す」ような発作性の痛み、心因性疼痛
抗不安薬: 筋緊張、攣縮による痛み、心因性疼痛
抗うつ薬: 神経因性疼痛、心因性疼痛、特に持続的な痛み
記載:おりたメンタルクリニック医師
■オンライン診療メンタルヘルス院について■
休職相談を扱う"オンライン診療専門"の
「オンライン診療メンタルヘルス院」もあります。
休職について悩まれている方は、お気軽にご相談ください。